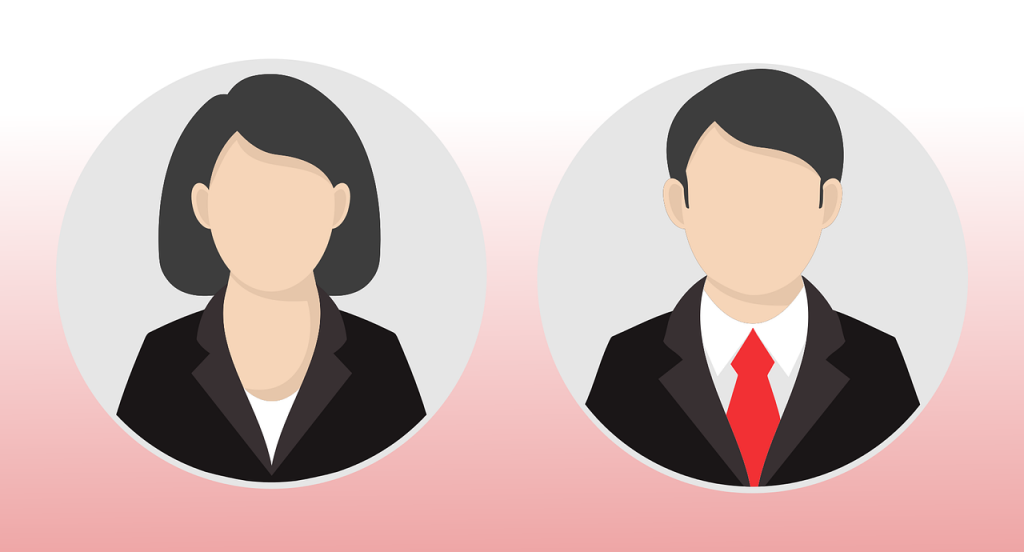グローバリズムとローカリズム。
相対するこの二つの言葉を合わせるとグローカリズムっていう言葉になるらしい。世界中がSNSで繋がった今、僕らはSNSを介して国境を越え、時差を越えて世界中の動向を瞬時に確認できる。そんな世界中の日常風景が気軽に覗けるようになった今だからこそ、均質化をもたらすグローバリズムばかりではなく、コンサバなローカリズムの中に生まれる”グローカリズム”に注目したい。
全てこの街の人たちの支え合っての今だよ
オアシススケートボードショップ
ハワイ島ヒロのダウンタウンからほど近いところに位置する、Daniel Madsen が店長を務めるスケートボードショップ。小規模の店舗だが、店の横にランプやウォールアートがあり、ローカルのスケーターやデザイナーまで幅広い人が集まる。
──ビジネスを始めたのはいつ頃で、なぜ始めたの?
Daniel:グラフィックのプリントを始めたのは2004年で、この店を構えたのが2011年のこと。僕はもともとアメリカ本土西部に位置するミネソタの小さな街出身なんだ。スケボーをする子なんて10人くらいしかいない感じの本当に小さい街で。だから、そこから遠く離れて初めてヒロに来た時「なんて大きい街なんだ」て思ったよ。スケボーをする子供がたくさんいるし、スケートボードショップができそうな場所もたくさんある。その頃はまだショップもパークもなかったんだ。だからこそここに店を構えるのがいいと思えたし、それができるチャンスをたまたま掴めた。小さな街で小さなショップを構えることってかっこいいだろ?

──でも外からやって来て、1からビジネスを始めることって簡単ではないよね。どういう戦略で始めた?
Daniel:全てこの街の人たちの支え合っての今だよ。僕たちはただ新しいビジネスを始めただけだあって、みんな僕たちが何をするか、そしてそれに参加することを楽しみにしてくれた。ショップもパークもなかった時代だからね。ショップという形でみんなが集まって、スケボーができて、そこで出会った人たち仲良くなることができるコミュニティをみんなが必要としていたんだと思う。それに自然な成り行きではあったのだけれど、僕らはローカルブランドを店頭で売るようにした。ここに並んでいるボードは全部違うブランドのもので、ヒロのローカルのデザイナーがデザインしたものを直接持ち込めるようにすることで彼らにも販売することができる場所を提供できたし、僕らも可能な限り多くのブランドを扱いたかった。それに彼らのデザインしたものは大きなブランドと比べて若干安めの商品として提供できるからそれもよかったね。それに僕らがここに初めてきた頃にローカルに出回っていたスケートボードの質は正直ダメだったんだ。だから商品の質にもこだわったよ。
ローカルとの繋がり

──ローカルとの繋がりはどう作り上げ、同時にどうローカルに貢献しようとしている?
Daniel:少し精神的な話になっちゃうけれど、この街の人たちって幸せそうだよね(笑)みんな幸せそうだし、アロハ精神というわけではないのだけれど、街の人たちのそういうところが繋がりやすさに繋がるのかな。
両方に言えることで、スケボーのコンテストを開いたり、パークを作ろうとしていることがそれにあたるのかな。実はショップをスタートする前からブランド会社そのものは経営していて、その時からスケボーのコンテストやイベントを開催するようになったんだ。その頃からサーフィンやスケボーをベースにしたブランドそのものは他にもあったんだけど、彼らは地域貢献だとかは気にしていないように見えた。ただ新しい商品を出すみたいな感じで。
他に僕らみたいにイベントを開催する店もなかったし、僕ら自身もその時はもっと純粋にただ楽しもうとしていただけだったね。現在進行系のものでいうとこの街に新しいパークを作る運動をして、この運動に参加したい人を探している。まずは市長に嘆願書みたいなのを通さなくちゃいけないから現時点では小口の募金のみを募っているというのが現実。計画そのものはすでに五年から六年目に突入していて、ここまで来ると時々ダメかとも思ってしまうこともあるんだけど、長期的な視点を持つようにしているよ。
ここができれば合法的にスケボを楽しめる場ができるし、そういう場がないから実現すればみんなが集まれる場を提供するという形で地域貢献できる。建設時は小さな設備から全体まで手作りで進めたいと思っているんだ。ここから2ブロックくらいの公園を使いたいと思っていて、店から近いから立地もいいし、しっかり使われていない土地を有効活用できる。
実は今この公園は子供向けの公園だったはずが、ホームレスやドラッガー、喧嘩なんていう治安の悪いものが集まっちゃっているんだ。だからそれをスケボーで変えたい。つい最近計画書を市長に提出して、このパーク計画の意義を伝えたんだ。今後もまだミーティングがあって、もし承諾されれば建設費への募金金額の限度も引き上げることができる。実際にすでにこの計画に対して他のみんなが出資をしてくれそうな雰囲気もさらにでてきているし、土地さえ手に入れればよりそれが具体的になるはず。この予感があってることを願うばかりだよ。

──パーク建設やショップ運営を含め、どのようなつながりで動いている?
Daniel:パークに関していうと自分たちですでに何回かパーク建設に関する募金を募ったりするイベントをローカル向けに開いたりしている。ショップ運営に関しては、例えばカウアイ島でファッション会社を営む友達に「ボードはどこで作っているの?」て聞かれたから、それならいっそのことコラボレーション商品を出そうということで一緒に動き始めた。
あと例えばここに置いてあるうちの一つのブランドのデザイナーはここ出身で、とにかくソーシャルメディアでも公衆でも彼のブランドの話をしまくるんだ。それで彼が彼のアイテムがオアシススケートボードショップにおいてあるぜって宣伝することでみんなが寄ってくれるようにもなる。逆に大きいブランドを入荷したことに関してはみんなあまり気にしなくて、これは予想外の反応ではあったのだけれど、こういうローカルブランドがローンチされる時の方がみんな楽しみにしてるんだ。
僕らの存在はパズルの1ピースみたいなもの
──ローカルでショップを経営する利点、欠点というのは??
Daniel:少しローカルとのコミュニティーとの繋がりの話に戻るんだけど、僕たちが地元でスケボーのコンテストを開催したりパーク建設を目指す一方、大型のショップは絶対にここではそういうことをやらない。ただ製品を販売して利益を得るだけ。彼らもコンテストを開くことはあるけれど、ロサンゼルスとか大きな街でだけなんだ。決してローカルの子供達向けのものは開催しない。そういう面でもローカルコミュニティと繋がったり、新しい機会を与えることができるから、僕たちにとってのアドバンテージはコミュニテそのものだね。
僕らの存在はパズルの1ピースみたいなものなんだ。都会ではよりスケボー関連のショップも人もあるから競争率が高いのに比べ、ここには僕らだけ。みんなが集まれるコミュニティがあって、彼らがこの店を知ってくれているんだ。欠点で言えば、この島には他にも数個ブランドはあるのだけれど、正直コラボレーションをするほどでもないものもある。コラボレーションするからには僕らも商品を売らなきゃいけないけれど、売れ行きが悪いものが残ってしまうこともある。

──最近になってヒロでもインスタグラムを始めとしたSNSが生活にかなり浸透してきたと聞くけれど、ビジネス面におけるソーシャルメディアやSNSの影響というのは?
Daniel:店を開店する前は古風ではあるのだけど、商品とは別にペーパーカタログも作っていたんだ。でもインスタグラムが台頭してからはカタログを読む人が少なくなった。その時はEmailやSNSで情報発信をする一方、他のスケートボードショップにも頼んで彼らに僕らの商品を販売してもらったんだ。で、店を開いてからは一旦メインランドにあるスケートボードショップへのアプローチをやめて、この店だけで販売するようになったんだ。その時にインスタグラムでの情報発信はかなり助かったね。商品情報から何から何まで発信できるし、僕らをただフォローさえしていてくれれば自然と情報を伝えることができるようになった。一方で商品を全て売り切るという課題に関しては、今通販サイトの解説を考えていて、それに合わせてネットカタログの作成も考えている。それもまたSNSがあるからこそできることになるね。再度他のショップへのアプローチをするのもより簡単になるはず。
マナ(ショップスタッフ):私にそれやらせてよ
Daniel:できるの?いいね、やってみてよ!

──店としての将来のビジョンは?
Daniel:まずはしっかりと製品を売ること、そしてもっとコラボレーションできる幅を広げたいね。実は日本を視野に入れているんだ。もちろん他の国もだけど、今はかなり日本を真剣に考えている。それが実現できたら最高だよ。
writer’s view
外からやってきた人がローカルのコミュニティに受け入れられ、今や店とローカルが持ちつ持たれつの関係で街づくりを進めている。これこそ素敵なグローカルの一例だ。公園の建設計画もそうであるし、取材中に店員のマナがカタログ作成の制作を任せてほしいと申し出たことに二つ返事でOKを出すところなど、地域貢献や若者への機会提供をしたいというDanielの思いは実際に目に見えるものとして感じられる。取材後たまたまマナに会ったのだが、すでにカタログ作成はマナを中心に進んでいるようだ。そして僕自身、この店に通ったことで新しい友達ができたし、今回の取材も彼らのおかげでできた。「人の繋がり」が生まれ、新たな何かとして育つ店。ディスアドバンテージではなく、このローカルだからこそできることを伸ばし、楽しみ続けようとするローカルショップの動向は、きっとこれから違うローカルでショップ運営をしようとする人たちにとっても好例となるのではないだろうか。
Text: S.Kamegai (READY TO FASHION MAG編集部)